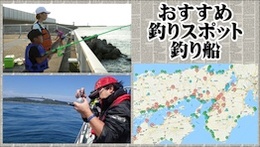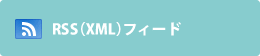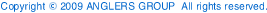『8EN海岸』とマットソニック理論 2012-08-09 PM12:42
今日はまた新たな釣具を紹介します。
コレです。
『8EN海岸(バエンカイガン)』
大きさはこんな感じ
けっこう大きいです。
重さは3~8gくらい、水を吸わせるとプラス3gくらいになります。
その名のとおり「海岸」で使うことを想定したバエンになります。
ヒラメ、マゴチなどを釣る為のバエンです。
もちろんスズキなんかにも対応させたいと思っています。
これはオレンジ北村クンにテスト協力してもらっています。
オレンジ北村ブログ
http://www.fimosw.com/u/atushi
どの重さ、長さがベストなのか、ずっと悩んでいるのですが昨日はバッチリ決まりましたね(笑) 今日は8ENを封印し、プラグルアー使用の北村氏は沈黙・・・(ウグイひとつ)
今日は8ENを封印し、プラグルアー使用の北村氏は沈黙・・・(ウグイひとつ) ワタクシの「8EN海岸」炸裂(しかもスズキばかり)
ワタクシの「8EN海岸」炸裂(しかもスズキばかり)
※足場が非常に高い釣り場なので、ワタクシどもの使用している「テスト用海岸8EN」は緩めると簡単に魚が外れるように改造してあります。
あっ、ヘルメットかぶってる意味は「脱ぐのメンドくさかったから」それだけね(笑)
しかし、哺乳類の皮膚ってなんでこんなに喰いがいいのだろうか?
ホント不思議!
タンパク質とコラーゲンが主な成分だから?
柔らかいから?
前回すこし触れた「マットソニック理論」がすべてなんでしょうね
じゃあ、もう少し詳しく説明しましょうか「マットソニック理論」を・・・
ちょっと小難しい内容になりますが、ゆっくり読んでみてください。
【マットソニック理論】
1、水中に於ける情報処理
あらゆる水中生物は、水中生活をするために情報処理の能力を有してなければなりません。
もしそれが無いならば、1日たりとも生活はできません。
水中は空気中と異なり、情報の伝播するスピードや種類が違います。
要するに空気中で当たり前の情報処理技術は、水中に於いて役に立たないということです。
しかし、何が水中生活の優先順位の高い要因なのかを真面目に考察することは今までありませんでした。
なぜならば、およそ空気中での情報処理技術の概念では想像しえないカテゴリーであるからです。
しかしここで明確なのは、水中生活生物がどのように情報処理をして。どんな感じに受動しているかはニンゲンには全く理解できていないということです。
また、夜間に多くの水中生物が活発化するためには光学的技術ではない未知の技術が不可欠なのです。
2、仮定としての音響
もともと水上生活をしていたが、後に水中生活に移っていった哺乳類といえば、イルカとクジラですね。
この哺乳類達に共通していることと言えば「極めて目が悪いことと水中コミュニケーション手段として音響に頼っている」という事が挙げられます。
イルカ類が水中で発する音響は機械では計測可能であり、万人の知るとこでしょう。
さて、一般的に音響で何がわかるのか?
実は光学的な計測によりいろいろなことがわかります。
たとえばですね、大きさ、距離、硬柔、速度はもとより実は内部構造すらも解析可能なのです。
物を壊さずに内部構造を観測するにはエックス線や電磁波や音波を使用することは一般的に理解されていますよね?
ということは、音響という情報処理はかなりの万能な技術であり、特に水中での優位性では右に出るものがないということでもあります。
ゆえにイルカ類は光学的なセンサーたる目が悪いにも関わらず、水中を超高速で正確に移動することが可能であると言えるのです。
3、計測できないものは世の中に無いものなのか?
さて、イルカ類の研究はすでに人間が持ち合わせている機械で計測できるということから始まります。
イルカ類以外の魚類に関しては計測出来ていないという事から何も情報がありません。
計測できてはじめて存在や概念が定義できます。
しかし、計測できないものは「全く世の中に無いもの」とも言えないことも考慮すべき点です。
この計測できない音響を【マットソニック】と表現しているんですね。
「ツヤ消しの音響」という意味の【マットソニック】。
そういうことです。
水中での機敏な動きやエサを漁り、敵から逃げる為には相当に早い伝播速度を有する情報処理技術が不可欠です。
しかも光学的であってはならない・・・
とすると、「音響しかなかろう」という消去法から導かれた考え方の為、当然、計測はできておらずに推測の領域を出てはいません。
しかし、「計測できないものは世の中に無い物なのか?」
この観点から推測して計測できたと仮定するならば、必ずこうなるという実験を繰り返すことで”自らの考え方”にリアリティを付加させることこそ”客観的な視点”だと思うのです。
「計測できないものは、世の中に無いものなのか?」
命題はこれだけです。
4、水中で何がわかるのか?
マットソニックの基本は音響です。
ならば、水中で何がわかるのか?
おおよそ生活していく為のほとんどが感知できるとするならば、先に述べた大きさや速さ、硬柔は感知できているはず!
しかし我々ニンゲンが音響で何を感知できるかといえば、加えて内部構造なのです。
とすると、魚も内部構造を少なからず感知していると考えたほうが納得できますね。
しかししかし・・・
感知の精度となる怪しいのが魚。
ゆえに魚は”釣りの対象”となるのに対してイルカやクジラは”釣りの対象”にはなりません。
逆に言えば、感知能力が優れたイルカ類はニンゲンの釣り仕掛けをたやすく見破ることができ、そうでない魚は釣られてしまうのです。
極めて粗悪で精度が低い感知機能であるがゆえに釣られてしまうのが「魚」
なんですね。
こう考えてみると理解しやすいと思います。
音響は「体積」「表面積」「速度」「硬柔」によって、異なる価を示します。
少なからずそれらの分野においてある程度の完成なくして魚は釣れないものだと思います。
だとするならば、「釣りには何が不可欠なのか?」は自ずと理解できるのではないでしょうか。
マットソニックという未知なる概念が存在したとするならば、そういう仮定にすぎません。
5、マットソニックの応用と実戦
ここが一番気になるところではないでしょうか?笑
同体積ならば、表面積が大きいほうがマットソニックの価は大きい。
同速度ならば、体積の大きい方がマットソニックの価は大きい。
もし、音響という側面からマットソニックを捉えるならばそうなります。
しかし、マットソニックが水中情報処理技術に関与しているならば、マットソニック次第でなんとでも表現可能であるということです。
危険の演出からエサ獲りまで・・・
とすると、釣りに応用できるマットソニックの価は如何なるものなのでしょうか。
これは実験によってのみ得られる価であり、実験方法も多岐にわたり時間やエネルギーも費やすことになります。
初めに概念ありき。
そして論証と実験。
その結果に基づいて形になったものが「8EN」や「326」などの小林重工製品なんですね。
しかし、小林氏いわく、
「マットソニックの価を忠実に再現できているとは思わない」のだそうです。
なぜならば、未だに計測できていない音響であるためです。
「30年以上に渡って私の概念を凌駕し、また結果も凌ぐ表現が無いということを考えてみると、自ずと確からしさにも信憑性が出てこよう」と言っています。
水中で光学は意味を成さない。
ならば音響ではないのか?
しかも計測できていない音響があるのではないか?
これが「マットソニック」の考え方の次第です。
ちょっと難しかったですか?笑
ワタクシは最初にこの「マットソニック」という考えを聞いたときに、かなり理解できました。
衝撃でした!
いろいろと考えていたことがすっきりしたといいますか(笑)
今までの考えや経験とこのマットソニックがズバリ!と繋がったんですよね
やっぱあの人、天才やわ・・・笑
とりあえず、今はこの「哺乳類の皮膚」を使う意味を理解して使っていますが、とにかくスゴイと感じています。
「表面積の大切さ」は自分の中では長年の課題でした。
たしかに皮膚と言う素材、表面積がとんでもない!
釣れる原因はそこにあるんですね
う~ん、、、マイッタ!